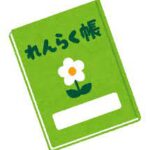※このサイトはアフィリエイト広告を利用しています
本日は、保育所における午睡(お昼寝)についての記事となります。

過去にこちらの記事で「午睡チェック」というものを紹介説明していますが、今回は午睡(お昼寝)そのものについてです。
なぜ今回午睡について紹介していくのかというと、保育所における「午睡」には大きな勘違い(誤解)と大きな課題があるからです。
保育所における午睡の勘違いと課題はなんなのか?
是非最後までご覧ください。
保育所における「午睡」の扱い

私は今まで単発も含めると20園以上で保育をさせていただく機会がありました。その全ての園で「午睡」の時間は設けられていました。もちろん中には寝ない子もいましたが・・・。
また、私は幼稚園で働いたことはありません。が、幼稚園教諭経験のある先生に話を聞くと、園によって寝る子もいたが「午睡」の時間が設けられているわけではない。ということでした。
おそらくほとんどの方は、保育園はお昼寝あり、幼稚園はお昼寝なし、というイメージだと思いますし、それで正解のようですが、保育所のルールの基盤である「保育指針」における午睡の扱いを見てみるとこのようになっています。
この指針内容の解釈は各々あるかもしれませんが、僕ら(保育園)に求められているのは、
- 安心、安全な睡眠環境を確保する
- 一律とならないようにする
といったことのようです。
しかし!
保育指針における「午睡」の扱いを、自身が体験している午睡(寝かしつけ)と照らし合わせると違和感を感じます。
保育園ではお昼寝はするもの。
一斉にお昼寝をする。
こういった経験をしてきたからです。
もちろん指針に定められているわけですから、自身の常識(経験)が間違っているのでしょう。
これが今回のテーマである、午睡の勘違いです。
午睡は決まり事なんだ、するもんなんだ。
これは大いなる勘違いだったのです。
次の項から「午睡」についての違和感と課題について考えを述べていきたいと思います。
安心、安全な睡眠環境を確保する
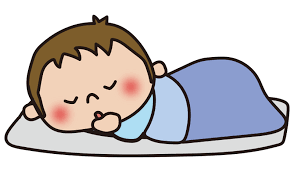
安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保する
実は、こちらの文言にもちょっとした違和感を感じています。
一見するとおかしな点は何も見つからないようですが、違和感を覚えるのは「安心」と「安全」の言葉の意味とバランス。
そもそも、午睡の際の安心とは何なのか?
という点です。
具体的に感じているのは、
- 子どもの寝る向き
- 室内の明るさ
です。
私は15年近く保育の仕事をしていますが、午睡のやり方もアップデートしています。
子どもの寝る向きは原則仰向け。横向きもできればなおすように、と指導を受けたことがあります。
室内の明るさは原則全灯。もしくはワンランクだけ下げた明るさ。
安全対策としては当然、と言えるかもしれません。
しかし!
子どもによっては寝る時の安心できる姿勢、というのは異なります。
また、全灯(明るい状態)は、安心して眠れる環境と言えるのか疑問です。
子どもの姿勢を変えることで起こしてしまうこともあります、ぐずることもあります。
明るいことでテンションが中々下がらない子もいます。
これが果たして「安心」と言えるのかどうか?
違和感を感じます。
これらはどちらも乳幼児突然死症候群を防ぐための措置です。
子どもの命を守るためのものですから、何にも変えることはできないでしょう。
ルールとしては、これからもこのやり方を徹底してやっていくべきなのでしょう。
ですが!
最も大切なことは、しっかり子どもを見る。ということだと思います。
乳幼児の午睡中の無呼吸症状というのは原因不明で起こりうるもの。それを防ぐ(早期発見)ためにはやはり子どもを見る、ということにつきます。
午睡中本当に午睡チェックのみに従事している職員が配置されているでしょうか?
「ながら」、になっていないでしょうか?
午睡時の人員配置や適切な役割分担が安心・安全な午睡環境を整える方法になると思います。
一律とならないようにする

睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。
これをかみ砕いていくと、「一斉の午睡」・「今は寝る時間」というやり方は指針上では正しい午睡とは言えないようです。
おそらくほとんどの園では乳児クラスを除いて、昼食後に一斉午睡が始まるかと思います。
「さあ、寝るんだよー」
「今は寝る時間だよ」
「寝なさい」
そんな声が飛び交います。
みんながみんな昼食後に眠くなって寝る。であればいいのかもしれませんが、そうでなければ「一斉に寝かす」、というのは「一律とならないようにする」、とは真逆な行いとなってしまいます。
「午睡」は子どもの成長を促す、子どもの身体を休める大切な活動です。
ですが、それも家庭環境や個人差に配慮する必要があるのです。
なので、午睡時間は、
寝たい子は寝る。寝たくない子は寝ない。で良いのです。
が!
・・・現実、それをやっていくと大きな問題が2つ出てきます。
- 寝ている(寝たい)子を起こしてしまう
- お昼の仕事が片付かない
どちらも現場で働いている先生にとってはとても大きな問題です。
寝たい子は寝る。寝たくない子は寝ない。だと、寝ない子のための遊ぶ環境を整えなければなりません。
他の子が寝ている間、じっと静かに待っている。必ずしもできるわけではありません。・・・いや、できないでしょう。
寝たい子の眠りを妨げないように遊べるスペース、遊べるおもちゃ、それを見る保育者。こういった物的環境・人的環境を整える必要があります。
そして、この環境構成をすることが「一律とならないようにする」の実現方法だと考えます。
また、
お昼の時間を利用して、先生たちは休憩のローテーションをまわしたり、連絡帳をはじめとした書き物を仕上げなければいけない。そんな状況が常ではないでしょうか。
その中で子どもたちが各々の活動をしていると、正直それが片付かない。といった思いが現実には出てきます。
それを解消するためには、各々活動する子どもを見る、という人的環境の構成がやっぱり必要となります。
また、人員配置、役割分担の見直しの中で無駄な仕事を見つけ、簡略化、効率化することも大いに求められるでしょう。
まとめ
本日は、保育所における午睡の勘違いと課題をみてきました。
午睡環境の安心・安全のイメージの違い。
保育所での午睡は「決まりごと」、「一斉午睡」に近い風潮がある中での、「一律とならないように配慮する」という保育指針の文言。
今後、主体的な保育と合わせて考えていかなければいけない事柄の様に感じます。
また、そのためには「環境の構築」が大切、特に人的環境の見直しが求められるでしょう。
保育士不足、配置基準の見直しが叫ばれている昨今。
「午睡」という角度から見ても、人員配置、役割分担、仕事の簡略化、は、子どもの保育所生活での安心・安全のために、今取り組むべき課題だと思います。

![]()